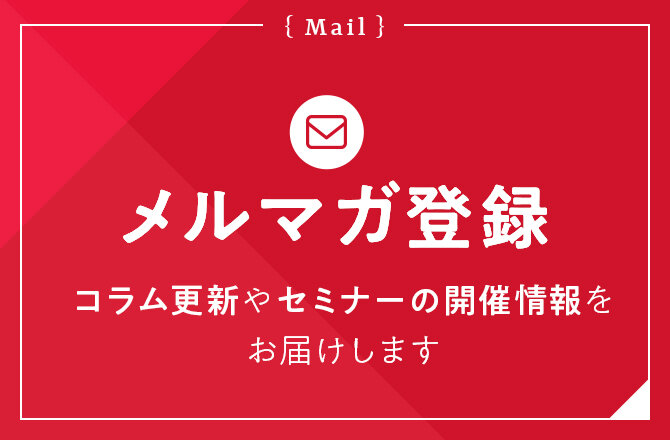事例
2021.12.22
VR(360度カメラ)で、学びに臨場感を。ICTで学びの可能性を広げる
目次
【背景】これからの社会を生き抜くために、ICTに親しんでほしい
2021年春、原宿外苑中学校に赴任した駒崎校長先生は、これまでの着任校でも意欲的にICT教育を推進してこられました。タブレットにVRグラス、ドローンなど、活用したツールも多種多様。そこには、これからの教育に対する強い想いがあります。
「私たちの仕事は、これからの社会を生き抜く子どもたちを育てること。そのためには、世の中の便利なツール(機器)を学校教育にどんどん取り入れて、先端技術(テクノロジー)の使い方も教えていく必要があると思っています。そうした経験が、生徒自身の“課題解決能力”を育ててくれるはずです。
たとえば校長として勤めていた小学校で、360度カメラのTHETAを導入、3年生の地域学習に活用しました。THETAをドローンに接続して、上空から自分たちの住む街を眺めたのです。平面の地図を見るだけでは感じることのできない『この方角は緑が多い、こっちの方角はこんなに発展してる』『こんな高いビルがあること、地図ではわからなかった』などといった感想が飛び出し、学びをぐっと深めてくれました」
これからの学びは、教員が一方的に教えるものではありません。子どもたちが仲間とともに考え、答えをつくり出す場面が増えていきます。そのとき、THETAやドローンなどの最新機器が、新たな発想を促してくれるのだと駒崎校長先生は語ります。
【状況/効果】360度カメラの映像は、さまざまな教育活動に大活躍
・バーチャル学校見学コンテンツの制作
原宿外苑中学校でTHETAがいち早く活用されたのは、バーチャル学校見学コンテンツでした。
「原宿外苑中学校のある渋谷区は、学校選択希望制が導入されていて、進学する中学校を区域外からも生徒が選べるようになっています。学校選びにおいて、施設は大きなポイント。しかしコロナ禍では、何百人もの方に学校見学にお越しいただくのが難しくなっていました。
そこでTHETAを使い、校内を360度撮影して、バーチャルの学校見学を実現したのです。操作性にも優れたTHETAで、見学映像の撮影・編集は3時間程度で済んだにも関わらず、保護者の方々や近隣の学校からは非常に好評をいただきました」 THETA 360.bizを利用した原宿外苑中学校様 バーチャル学校見学コンテンツ。実際に校内を回っているような没入感が感じられる。
THETA 360.bizを利用した原宿外苑中学校様 バーチャル学校見学コンテンツ。実際に校内を回っているような没入感が感じられる。
・360度カメラで、これまでにない地域学習を
バーチャル学校見学だけでなく、さまざまな授業への導入も検討されています。駒崎校長先生が以前勤めていた中学校では、農家の方が田植えの方法を指導する360度の映像を、生徒がVRグラスで視聴。1対1でじかに教わっているような没入感を味わい、田植え体験に取り組んだそうです。
また、田んぼに住む生き物の360度映像を活用して、同じくVRグラスで視聴することで、臨場感ある理科の授業にもつなげました。
「そのようにただ映像を見るだけでも充分興味深い授業になるのですが、子どもたちが自分で撮影した映像を使えば、さらに一歩進んだ学びができるはずです。
たとえばいま、渋谷区の小中学校と地域が協働して、『シブヤ科』という地域学習プロジェクトを進めています。さまざまな地域の課題を、子どもたちにも考えてもらい、ともに解決していこうという試みです。
そこにTHETAを取り入れて、街の様子を撮影し、これからの渋谷の在り方について考えてみる。自分たちや自治体、企業ができる取り組みについて検討してみる。アウトプットの質もより高められるよう、スタートアップ企業と連携して、THETAの映像を使ったプレゼンツールも開発しているところです。」
・今後欠かせないプログラミングにも
小中学校でのプログラミング教育が必修化され、小学校では、さまざまな教科のさまざまな場面で学習が組み込まれるようになっています。中学校では、技術家庭科の授業が中心です。
今後、課題解決のツールとして実際に「プログラミング」を活用できるようになってもらうためにも、ICTを取り入れて多様な学習機会を増やしたいと、駒崎校長先生は話します。
「初歩のプログラミングは画面上のアニメーションを動かすくらいですが、自分の組んだプログラムで実際に物を運んだり、なにかの映像を撮影したりするようなことができるようにしたい。そうすれば、プログラミングが課題解決のツールになることで、生徒がもっと見方や考え方を広げ、興味を示すと思います。そのためにも、THETAやドローンといった最新機器を組み合わせて、学びを深めてあげたいと考えています。渋谷区は地域に多くのIT企業もあるので、エンジニアの方に来ていただくような機会も確実に増加しています」
・ICTをどう学びに活かすか、試行錯誤しながらみんなで考える
GIGAスクール構想が広がるなか、タブレットなどを導入しても、それをうまく使いこなせずに悩むこともあるかもしれません。しかし、これほどさまざまなシーンでICTを活用している原宿外苑中学校に、特別な研修などはないと言います。
「他校から『ICTが苦手な先生はいませんか?』『使い方は研修していますか?』などと質問をいただくことがよくありますが、どちらも答えは『いいえ』です。いまの機器は誰でも簡単に使えるようになっているので、導入にハードルはありません。
大切なのは、そうした便利な機器をいかに学びと結びつけるか。社会でどんなふうに使われているかを踏まえて、学校での使い方を発想していくことです。それも教員主体ではなく、子どもたちが主体的に考えていけるような状況をつくっていきたいと思っています。
もちろん、使っていくうえで失敗はあります。360度カメラの映像に撮影者が映り込んでしまったり、スムーズにWi-Fi接続ができなかったり……。でも、そうやって試行錯誤している姿も、子どもたちは見て学んでくれています。うまくいかないオンライン授業のときには、生徒からチャットで応援メッセージが届くこともありました。
学校は間違えるところなのだから、多少失敗してもかまわない。教員も生徒もともにトライ&エラーを繰り返して、学んでいけばいいのです。日本の学校にはまだあまりそういう空気がありませんが、教員と生徒に自走してもらえる環境をつくるのは、私たち管理職の仕事だと考えています」
【今後の展望】ICT活用を日本中に広げて、多くの子どもたちの未来を広げる
日本の子どもたちを未来社会でグローバルに活躍する人材に育てていくために、駒崎校長先生は多くの学校のICT活用支援にあたっています。
「先端技術と学びを融合させるといったことは、私が着任した学校など、一部の場でしか実践がされていないかもしれません。でも、このままでは日本から世界に羽ばたく人材がまったくいなくなってしまう。私はそれくらいの危機感を持っています。子どもたちには、せっかく大きな可能性があるのだから、ぜひどの学校にも挑戦してほしい。だからこそ、何をどんなふうに取り入れて、どう活かしているかの情報発信は徹底的にやるよう心掛けています。学校Webサイトや不定期発行の『校長室だより』などで、ICTの取り入れ方や活用目的などを説明しているのです。
また、最先端のものを現場で使える環境を用意してくれる、リコージャパンのような外部との連携も欠かせません。前例がない教育分野への進出は、もしかするとうまくいかないケースが出てくるかもしれないのに、チャレンジングに連携をしてくれます」
生徒たちに、ICTを使った学びをもっと身近に感じてもらい、これまで以上に学ぶ意欲を刺激すること。そして何か困ったときに「あの機器を使ってみようかな」と柔軟に発想できる下地をつくること。「こうした体験が必ず、子どもたちがこれからの未来を切り拓くきっかけになると信じています。未知の挑戦に批判があっても、勇気をもってチャレンジを続けたい」、未来への子ども達の可能性を想いながら駒崎校長先生は最後に語りました。「子どもたちは我々の『未来』そのものです」。